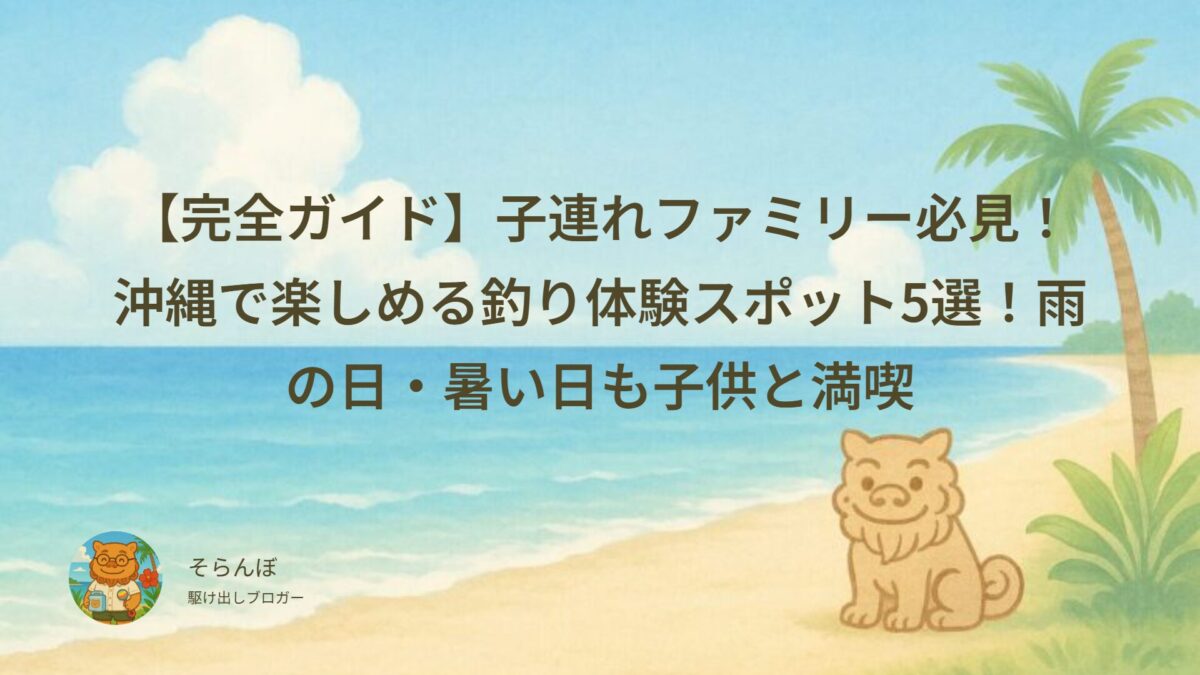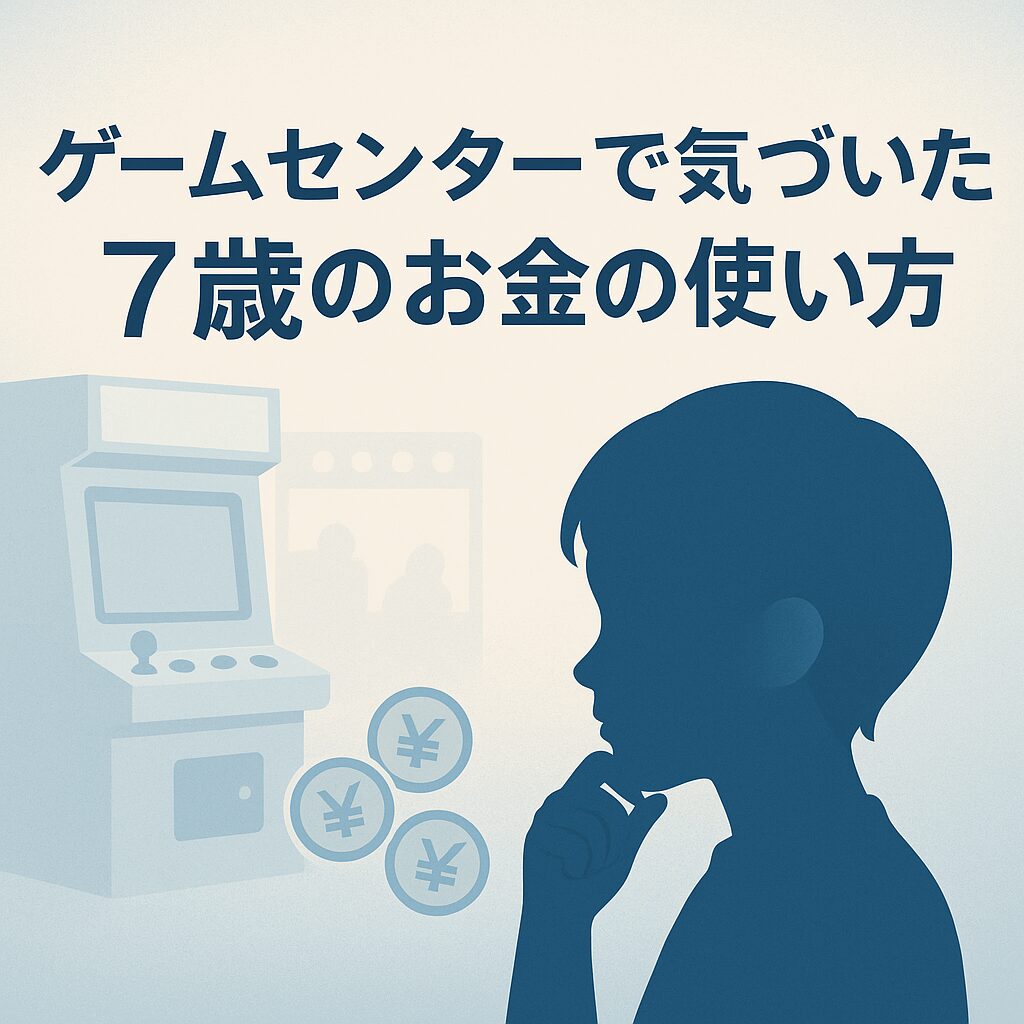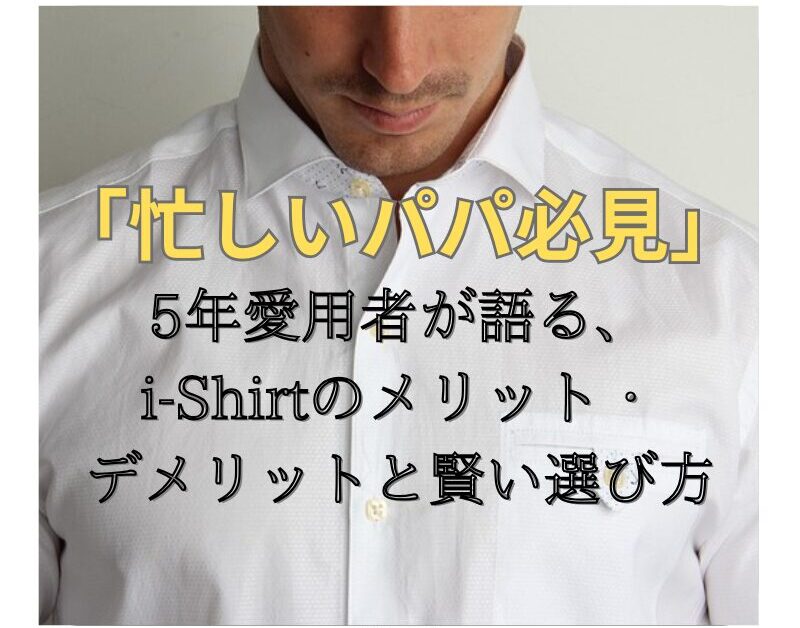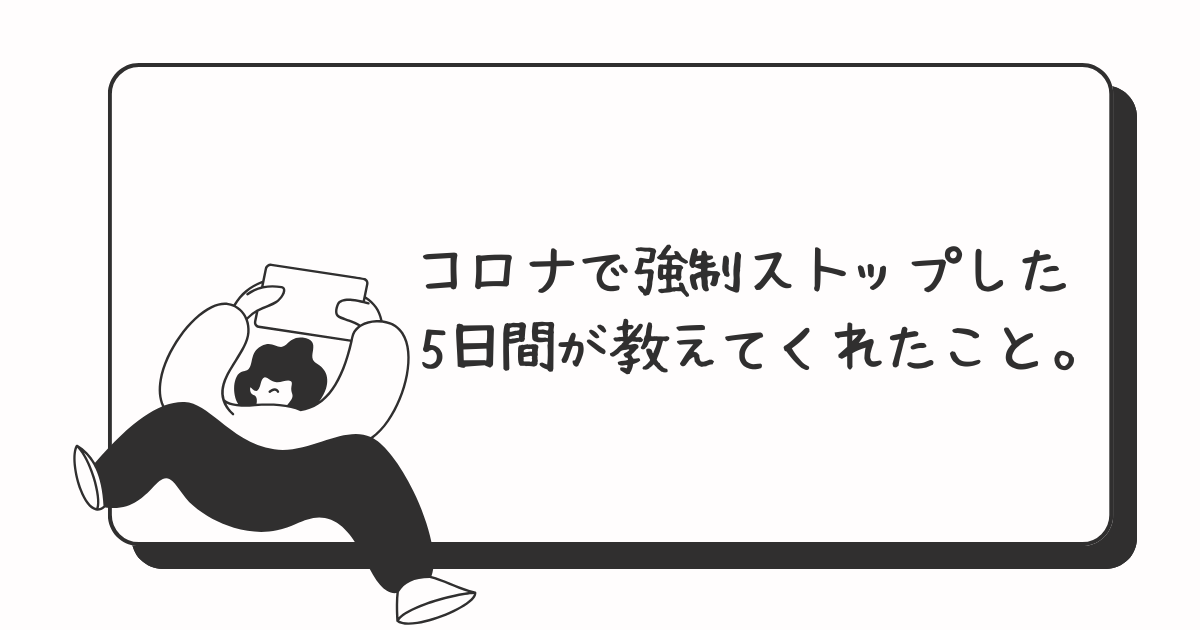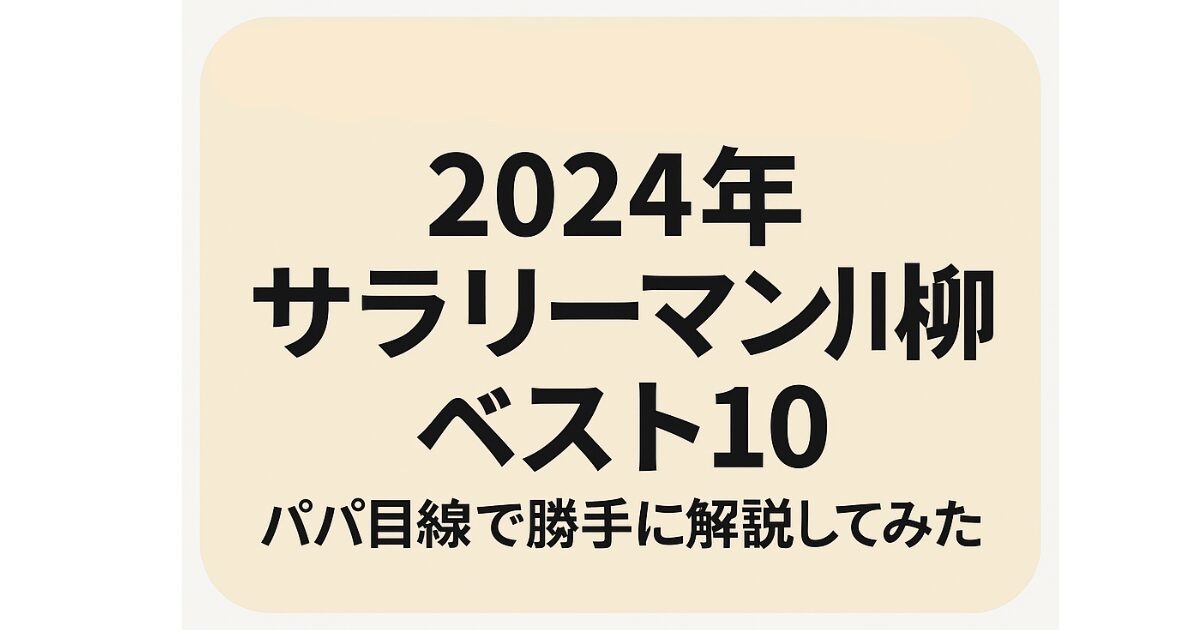子どもの急な発熱で困ったら?共働きパパが実践する仕事と看病の両立術
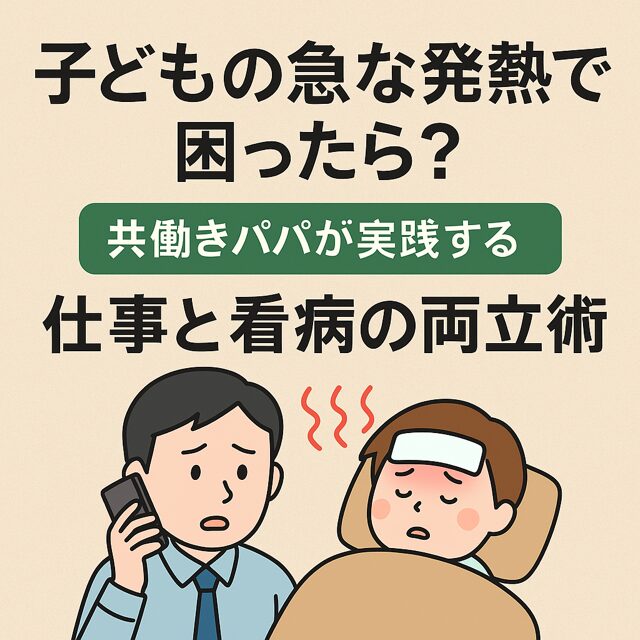

朝6時。息子の体がやけに熱く感じて、慌てて体温計を当てると――38.5℃。
「…嘘でしょ、今日に限って…」
共働き家庭にとって、子どもの急な体調不良、特に発熱は、仕事と看病の両立をどうするかという大きな課題です。妻は会議、僕は欠員対応で休みづらい。それでも目の前の子どもは、明らかにしんどそう。
我が家でも何度も直面してきた「子どもの体調不良」という緊急事態。この記事では、共働きパパが実際に経験した、仕事・病院・看病をどうバランス取り、この困難を乗り切るかについて、リアルな体験をもとにまとめました。
1. 焦らない判断が肝心!子どもの発熱・体調不良時の見極めポイント

子どもが不調な朝に一番大事なのは、**「焦らないこと」**です。まずは、我が家で意識している判断ポイントと、病院に行くべきかの基準を紹介します。
我が家のチェックポイント
体温だけでなく”顔色・声のトーン・動き”も見る 熱があっても元気か、ぐったりしているかを確認します。
ぐったりしているか、食欲はあるか 普段との違いを見極める大切なサインです。
夜の睡眠状態や、咳・嘔吐の有無 総合的に判断するために、夜間の様子も思い出しましょう。
基本的には、迷ったら病院に行くようにしています。
ただし、コロナやインフルエンザが流行中のときは、少し様子を見ることもあります。というのも、発症直後だと検査に反応しないことがあるからです。
逆に、ぐったりしている/高熱が続く/呼吸が荒いなどの場合は、迷わず受診しています。
受診判断の具体的な基準
- 朝の時点で38.5℃以上+ぐったりしている → 受診
- 熱はあるが元気・食欲あり・風邪症状なし → 様子見+昼に再測定
- 咳・嘔吐・下痢がある → 原因不明な場合は受診(感染症の可能性も)
また、かかりつけ医が休みの場合に備えて、事前に近隣の休日診療所や夜間診療の情報をメモしておくと安心です。我が家では、冷蔵庫に連絡先を貼っています。
2. 小児科受診の待ち時間を短縮する5つのテクニック

小児科は、時間帯によって待ち時間が大きく変わることも。我が家では、次のような工夫でなるべくスムーズに受診できるようにしています。
1. Web予約を戦略的に活用する
小児科によっては、朝8〜9時台からWeb予約がスタートします。「とりあえず予約 → キャンセルOK」な場合は、早めに枠を確保しておきましょう。
予約開始直後に埋まる人気クリニックもあるので、事前に時間チェックは必須です。
2. 受付だけ先に済ませる作戦
午後の受付開始後に**「受付だけ済ませ」て、子どものお迎え後に再度病院へ向かう**という方法も、我が家では選択肢のひとつとして活用しています。これで夕方の混雑を避けながら、確実に診察を受けることができます。
3. 時間帯の狙い目を知る
我が家のかかりつけ小児科では、受付開始の15分前には現地に行くことで、診察の順番が早くなり、1時間以上の待ち時間短縮になることも。
時間帯別の混雑パターンも把握しておくと便利です。
- 10〜11時台は比較的空いている(登園・登校後の時間帯)
- 夕方は再診の子が多く、混雑しがち
- 土曜午前は激混み(学校・保育園が休み+日曜は休診のため)
夕方の混雑状況によっては「受付打ち切り」となるケースもあるので注意が必要です。
4. 持参物で待ち時間対策
診察をスムーズに進めるため、また子どもが快適に過ごすために、以下のものを持参しましょう。
基本の持参物 診察券・保険証・お薬手帳、母子手帳(必要に応じて)
待ち時間対策グッズ 小さなおもちゃや絵本、水分補給用の飲み物、タオル(汗拭きや寒さ対策)
5. 予防的受診という考え方
熱がなくても、風邪の初期症状が出始めたときには、「薬がない状態で悪化させないように」と、早めの受診を心がけることもあります。前もっての対応が、子どもの体調の安定や回復のスピードに良い影響を与えていると感じています。
3. 誰が休む?共働き夫婦の看病役割分担術と調整のコツ

病院を受診するかどうかが決まったら、次に直面するのが――**「誰が子どもを見る?どちらが休む?」**という現実的な問題です。
我が家でも毎回スムーズにいくわけではありません。その都度夫婦で工夫しながら、「なるべく納得感のある着地」を目指しています。
我が家の基本的な考え方
我が家には明確な「ルール」はありませんが、ざっくりとした方針として:
- その日の**「勤務の融通がききやすい方」**がメインで看病
- どうしても外せない予定がある場合は、できるだけ前日夜のうちに共有
- 半休/時間休を**「分け合う」**という柔軟さも大事に
仕事の忙しさや会議の有無、休みやすさは日によって違うからこそ、「どちらかが当然やるべき」という固定観念は持たないようにしています。
夫婦での具体的な調整例
たとえば朝、子どもの発熱がわかった瞬間。その場で「どうする?」という話になるのですが、我が家ではこんなふうに対応しています:
妻「今日どうしても午前が人がいなくて…午後なら調整できるかも」
夫「OK、午前は俺が見るよ。午後から交代で大丈夫そう?」
こうやって、どちらか一方に負担を偏らせないように調整しています。半休や時間休を効果的に活用し、夫婦で柔軟に看病時間を分け合うのがポイントです。
働き方に応じた対応スタイル
私(パパ)はサービス業で、11時・12時出勤の日が多く、午前中は時間の融通がききやすい働き方です。そのため:
- 朝は私が看病 → 妻の職場近くまで子どもを連れて行き、途中で引き継ぎ
- 午後の休憩時間を長めに調整し、15時〜17時ごろまで面倒を見ることも
こんなふうに、「すき間時間を組み合わせる」スタイルで乗り切ることがよくあります。
外部サポートの活用も視野に
毎回夫婦どちらかが対応するのが厳しいときは、祖父母などの身近なサポートも検討します。
我が家の場合 どうしてもダメな日は祖父母にお願いすることもあります。事前に「○○のときはお願いするかも」と伝えておくと、急な依頼もスムーズです。
その他の選択肢 病児保育やファミリーサポートなどの地域サービスも活用できます。ただし、事前登録や利用方法の確認が必要な場合が多いので、事前に調べておきましょう。
病児保育については、以下の公的情報や全国の施設を検索できるサイトも参考にしてみてください
- 全国病児保育協議会 [https://byoujihoiku.net/sisetu/]
4. 子どもの看病中に役立つ具体的なコツと準備

いざ看病となると、普段の育児とは違う対応が必要です。少しでも子どもが楽に過ごせるように、我が家で実践している具体的なコツを紹介します。
環境づくり
静かで薄暗い部屋を用意 光の刺激を避け、落ち着いて休める環境を整えましょう。
湿度は50-60%を目安 加湿器や濡れタオルを活用して、空気が乾燥しないように注意します。
体温調節しやすい服装 前開きの服やパジャマなど、着替えさせやすいものが便利です。
水分・栄養補給
少量ずつ、こまめに水分補給 脱水症状を防ぐため、アクアソリタなどの経口補水液も活用しましょう。
食欲がない時は無理強いしない 食べられるものを少しずつ与えるのが基本です。
消化の良いものから徐々に おかゆ、うどん、バナナ、ゼリーなどから試しましょう。
症状別の対応
発熱時
- 解熱剤は医師の指示に従って使用しましょう
- 体を冷やしすぎないように注意し、氷枕よりも冷却シートや濡れタオルで優しく冷やすのがおすすめです
咳・鼻水
- 部屋の加湿を心がけ、喉の乾燥を防ぎましょう
- 上体を少し起こした姿勢で休ませると、呼吸が楽になることがあります
4-1、 我が家の看病セット一覧:いざという時に役立つ厳選アイテム

子どもの急な体調不良時、家にあらかじめ準備されているグッズがあると、パパ・ママの焦りも少し和らぎます。ここでは、我が家で実際に使用している、非常時に役立つおすすめ看病グッズをご紹介します。
医療用品
| アイテム | 用途・ポイント |
|---|---|
| 体温計(2本体制) | お家用、外出用、予備があると安心感が違います。子どもが嫌がっても、サッと別の体温計で測れるのは地味に便利です。 |
| 冷えピタ・保冷枕 | 子ども用サイズも複数用意しておくと、おでこ用や脇の下用など使い分けができて便利です。熱を下げるだけでなく、本人も快適に過ごせます。 |
| 吸入・吸引機 | 鼻水で苦しそうな時や、咳がひどい時に自宅で手軽にケアできると、病院に行く手間も省けます。うちは病院で相談して購入しました。 |
飲食関連
| アイテム | 用途・ポイント |
|---|---|
| アクアソリタ・アクアライト | 発熱や下痢、嘔吐などで脱水症状が心配な時に大活躍。効率的に水分補給ができるので、常備はマストです。 |
| ゼリー飲料・プリン | 食欲がない時でもスルッと食べやすく、栄養も補助できる強い味方。子どもが好きな味をいくつかストックしておくと良いでしょう。 |
| ポカリ粉末 | 非常用としてストックしておくと、水さえあればいつでも作れるので、買い置きを忘れがちな時でも安心感が違います。 |
これらのアイテムが揃っていると、急な発熱や体調不良にも落ち着いて対応できます。
もちろん、必要に応じて病院やドラッグストアで購入できますが、いざという時に慌てないよう、普段からチェックして準備しておいてくださいね。
私が愛用している吸入器の情報はこちら👇
家庭用ネブライザー おすすめ【4年愛用パパ本音レビュー】ミリコンキューブ KN-80S選び方・使い方ガイド | 喘息・風邪対策
5. 共働きパパの仕事と看病の両立!職場との関係づくりとフォローアップ

「子どもが熱を出したので休みます」──このひと言を伝えるときの気まずさ、共働きパパなら誰もが経験があるはずです。周囲への申し訳なさと、子どもへの心配が重なり、心がザワつく瞬間ですよね。
特に共働き家庭では、仕事への影響をいかに最小限に抑えるかが大きな課題になります。このパートでは、我が家が実践している職場との関係づくりと仕事のフォローアップ術を紹介します。
普段からの「信頼貯金」が大切
急な休みは避けられません。だからこそ日頃からの準備がカギになります。
業務の見える化 プロジェクトは共有ファイルで管理し、日々のToDoリストもチームで共有しましょう。重要な連絡先や手順書も整理しておくとスムーズです。
心理的な準備 「子どもが小さいので急に休むかもしれません」と事前に伝えておくと、理解も得やすいです。繁忙期など忙しい時期は、代替案を用意したりチーム内で「お互い様」の雰囲気作りも大切です。
テレワークや時短勤務制度の活用 もし利用できる制度があるなら、積極的に活用できるよう、日頃から職場と相談しておきましょう。
急な休み時の連絡術
早めの連絡 可能であれば始業前に、上司や同僚に連絡しましょう。
具体的な伝え方 「本日、子どもの発熱のためお休みをいただいております。緊急の〇〇については、△△さんにご確認ください。」のように、簡潔かつ引き継ぎ先を明確に伝えることが重要です。
復帰予定日の目安を伝える 「明日は出勤予定です」など、見込みを伝えることで、相手も動きやすくなります。
復帰後のフォローアップ戦略
信頼回復は行動で示しましょう。
復帰初日にやること
- 助けてくれた人への感謝の気持ちを具体的に伝えること
- 任せた仕事の状況を確認し、遅れた分はリカバリープランを立てることが重要です
「お互い様」の関係を築く
- 他の人が休むときは積極的にカバーし、時には残業や休日出勤でバランスを取ることも必要です
- 長期的には「この人なら安心」と信頼されるよう、普段から高い業務クオリティと先回りした提案を心がけてください
6. 男性育児参加の重要性:パパが看病に関わることの意味

まだ驚かれることもある「パパの看病休み」。
「奥さんは?」 「パパが看病できるの?」
「大変ですね」(同情の言葉)
こんな反応を受けることもありますが、パパが積極的に関わることで得られるものは大きいです。
家庭面でのメリット
妻の負担が減る ワンオペ育児になりがちな看病において、パパの協力は妻にとって大きな助けになります。
子どもとの信頼関係が深まる 弱っている時に寄り添ってくれるパパの存在は、子どもにとって特別なものです。
夫婦のチーム感がアップ 困難を一緒に乗り越えることで、夫婦の絆がより一層強まります。
仕事面でのメリット
「家族を大切にする人」として評価される 結果的に職場からの理解や信頼につながります。
職場の理解も広がる パパが育児参加する姿は、職場全体の多様な働き方への理解促進にも貢献します。
多様な働き方への理解促進 男性の育児参加が当たり前の空気を作ることで、職場の環境改善にもつながります。
個人面でのメリット
子育てスキルや緊急対応力が身につく 普段とは違う状況での対応は、自身のスキルアップにもつながります。
人生の優先順位が明確になる 仕事と家庭のバランスを深く考えるきっかけになります。
▶︎ パパ目線の育児については、こちらの記事もおすすめ
→「子どもがお風呂を嫌がる…?パパでもできた!楽しく入れる工夫5選【3〜6歳向け】」
まとめ|仕事と家庭の両立は「技術」と「準備」

子どもの急な体調不良は、共働き家庭にとって避けられない試練です。しかし、適切な準備と夫婦の協力、そして職場との良好な関係があれば、きっと乗り越えられます。
我が家の基本方針は…
- 子どもの健康を最優先
- 職場への影響は最小限に抑える
- 長期的な信頼関係を築く
この積み重ねが、働くパパとしても家庭人としても両立できる道につながると信じています。完璧を求めすぎず、「80点主義」で感謝の気持ちを忘れずに。
子どもの体調不良は突然やってきますが、事前に準備し、夫婦で協力し、職場と良好な関係を築くことで、乗り越えることは可能です。
この記事が、日々奮闘する共働きパパ・ママの皆さんの助けになれば幸いです。もし、この記事を読んで新たな気づきがあった方や、ご自身の体験談をシェアしたい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてくださいね!
「※このページでは、読者の皆様に役立つ商品をご紹介するため、アフィリエイトプログラムを利用しています。」